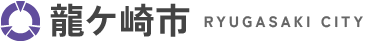「食品ロス削減月間」・「食品ロス削減の日」って?
食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年10月1日施行)第9条において、10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」と定められています。
食品ロスって?
「食品ロス」は、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。
実は、食品ロスの約半分は一般家庭から発生しています。(国内における年間の食品ロス約464万トンのうち、約233万トンが一般家庭から発生)
家庭での食品ロスは、過剰除去(野菜の皮の厚剥きなど)、食事の食べ残し、消費期限切れや賞味期限切れによって発生しています。
食品ロスは「もったいない」だけでなく、家計にとっても「無駄な出費」につながります。
食料資源を無駄にせず、ごみを減らして環境への負担を抑えるため、「もったいない」を心がけましょう。
- こちらのページもあわせてご覧ください
- 身近なことから食品ロス削減をはじめましょう
具体的に出来ること
外食では
- 店選びを工夫する:料理の量を選べる・余った料理を持ち帰りできるなど、食品ロス削減に取り組む店を選ぶ
- 量を考えて注文する:小盛りやハーフサイズなど、食べきれる分だけ注文する
- 宴会で発生する食品ロスを減らす:3010運動に取り組む
3010運動とは…
- 【乾杯後30分間】と【お開き10分前】は自席で料理を楽しみましょう、と呼びかけて、食品ロスを削減する取り組みです。
- ご友人・ご家族・職場の方など、身近な方への声掛けにご協力ください。
家庭では
- 適切に保存する:一度に使いきれない野菜や肉類などは、小分けまたは下処理のうえ、冷凍保存などによりストックする
- 残っている食材から使う:残っている食材を手前に、新しく買ってきた食材は奥に置いて保管すると、使い残しを防げます
- 食べきれる量を作る:自分の体調や、ご家族の予定(体調)を事前に把握・共有する習慣をつけるなどして、余分に作らないよう工夫する
作りすぎてしまった料理や、使い切れない食材があった時には、をご活用ください。
- アレンジレシピや、食材の使い切りレシピなどが1,000件以上投稿されています!
買い物の時には
- 必要な分だけ買う:「まとめ買いでお得!」といった言葉に惑わされず、消費しきれるかを考えて買う
- 重複を防ぐ:冷蔵庫や食品庫にある食材を確認してから買い物に行く
- 期限表示を確認する:すぐに食べる食品を買う際には、期限が長いものではなく、なるべく手前から選ぶ
もっとくわしく知りたい方は
お問い合わせ
本文ここまで